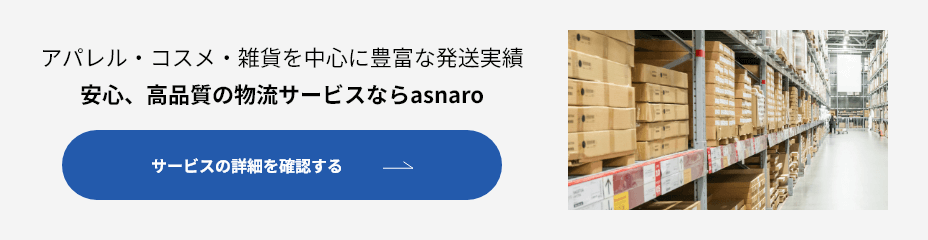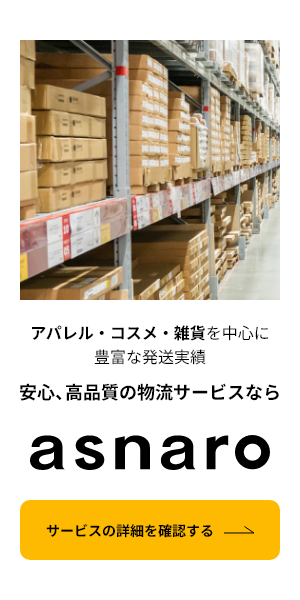物流業務の流れとは?出荷までの工程をわかりやすく解説

物流業務は、商品の入荷から保管、ピッキング、梱包、出荷、配送まで、多くの工程で構成されています。質の高い物流体制を整えるには、それぞれの工程でどのような作業が行なわれるのかしっかりと把握することが大切です。本記事では、そんな物流業務の流れをわかりやすく解説します。また、物流業務の最新トレンドや効率化のポイントもご紹介します。
目次
物流の6大機能
まずは、そもそも物流にはどのような機能があるのか見ていきましょう。
輸送・配送
物流業務の中核を担うのが「輸送・配送」です。一般的に「輸送」は拠点間の大量輸送を指し、メーカーから物流センター、物流センターから小売店への大口移動の際に活用されます。
一方「配送」はエンドユーザーや小売店など、最終的な届け先へ小口で商品を届ける工程です。トラック、船舶、航空機など、複数の輸送手段があり、コスト・納期・商品特性を踏まえて最適な手段を選定することが重要です。
また近年は、CO₂排出削減を意識した「環境配慮型輸送」や、EC需要の増加に伴う「ラストワンマイル配送」への対応も求められています。
保管
物流では、商品の適切な保管体制を整えることが重要です。出荷時期や需要に合わせた調整の役割を果たすとともに、在庫ロスや劣化を防ぐための品質管理も求められます。特に食品や医薬品、化粧品などは温度や湿度の管理が不可欠で、冷蔵・冷凍設備の整備が重要になります。
また、保管スペースの効率化も大きな課題で、ロケーション管理システムを活用することで最適な在庫配置を実現できます。適切な保管は欠品防止と顧客満足度向上につながるため、物流全体の安定稼働に直結します。
荷役
荷役は、倉庫内で商品を移動・仕分け・取り出す工程を指します。代表的な作業に「ピッキング」があります。これは、出荷指示に基づいて商品を正確に取り揃える作業です。従来は人力での作業が中心でしたが、近年はパレット、フォークリフト、自動搬送ロボット(AGV)などの荷役機器を導入し、効率化とミス防止が進んでいます。
また、EC需要の高まりにより小口・多品種出荷が増加しているため、スピードと精度を両立した荷役体制の構築が競争力強化に不可欠となっています。
梱包・包装
梱包・包装は、商品の保護と見栄えの両立を目的とする重要な工程です。「個装」は商品単体を保護するための最小単位、「内装」は複数商品をまとめた中箱、「外装」は輸送に適した形で商品を安全に保護するための段ボールなどが該当します。適切な梱包を行なうことで輸送中の破損防止や、保管時のスペースの効率性が向上します。
また近年では、環境配慮の観点から過剰包装の削減やリサイクル資材の活用も重視されています。適切な梱包は顧客体験の向上にも直結するため、物流業務全体において欠かせない要素です。
流通加工
流通加工とは、倉庫内で商品の付加価値を高めるための加工作業を指します。具体的には、検品、ラベル貼り、値札付け、ギフト包装、セット商品の組み立てなどが含まれます。これにより、販売チャネルや顧客ニーズに応じた柔軟な対応が可能になり、商品の付加価値を向上させることができます。
特にEC市場の拡大に伴い、小ロットかつ多品種の流通加工への対応が求められており、作業効率を高めるための自動化設備の導入も進んでいます。
情報システム
物流業務の効率化には情報システムの活用が欠かせません。代表的なものに、倉庫管理システム(WMS)や輸送管理システム(TMS)があります。これらのシステムを活用することで、在庫状況や入出庫データ、配送状況をリアルタイムで把握できます。ピッキングの効率向上、誤出荷防止、配送遅延の削減などが実現可能となります。
また近年は、AIやIoTを活用した高度な物流システムも普及しています。需要予測や最適ルートの自動算出など、物流業務全体の見える化と最適化が進んでいます。
物流業務の主要プロセス(フロー)
では、物流業務は具体的にどのような流れで行なわれるのか。前述の6大機能と重複する点もありますが、各工程の詳細を見ていきましょう。
輸送
物流の起点となるのが「輸送」です。メーカーや仕入れ先から物流拠点へ商品を移動させる「調達物流」、倉庫間をつなぐ「中継輸送」、最終消費者へ届ける「販売物流」など、目的に応じた輸送手段が選ばれます。
トラック、鉄道、船舶、航空機などの輸送手段があり、コスト・納期・品質のバランスを考慮して最適化することが大切です。特にEC市場ではスピード重視の小口輸送が増加しており、効率的なルート設計や共同配送の活用が求められています。
入荷検品
倉庫に商品が到着したら、まず入荷検品を行ないます。納品書や発注書と照らし合わせながら、数量や品目、外観、ラベルなどに誤りがないかを確認します。この工程で不良品や誤納品を見つけることで、後工程でのトラブルを防ぎます。
検品結果はシステムに即時反映させ、在庫データの精度向上につなげます。近年では、ハンディ端末やスキャナーを活用したバーコード・QRコード管理により、作業効率とミス防止の両立が進んでいます。
保管(ロケーション)
入荷した商品は、効率的なピッキングを可能にするため、適切なロケーションで保管します。ロケーション管理とは、商品ごとに棚やエリアを指定し、在庫を最適に配置する仕組みです。適切なロケーション設定により、作業員が商品を探す時間を短縮でき、倉庫内オペレーション全体の効率化につながります。
在庫管理
在庫管理は、物流業務の中でも非常に重要な役割を担う工程です。過剰在庫は保管コストの増加につながり、在庫不足は欠品による機会損失を招きます。適正在庫を維持するためには、需要予測や販売データの分析を活用した計画的な在庫管理がポイントです。
近年ではAIを活用した在庫最適化ツールや、リアルタイムで在庫状況を把握できるシステムの導入が進んでいます。これにより、在庫精度の向上だけでなく、キャッシュフローの健全化や顧客満足度向上にもつなげることができます。
ピッキング
ピッキングは、出荷指示に基づいて商品を棚から取り出す工程です。代表的な方式には、1人が複数注文を同時に処理する「トータルピッキング」と、1つの注文ごとに商品を揃える「シングルピッキング」があります。
EC市場の拡大により、小ロット・多品種のピッキング需要が増加しており、効率化が大きな課題となっています。バーコードスキャン、音声指示システム、ピッキングロボットなどの自動化技術を活用することで、作業ミス防止とスピード向上を両立できます。
出荷検品
ピッキング後は、出荷前に再度検品を行ない、商品・数量・ラベルなどに誤りがないかを最終確認します。この工程は誤出荷防止の要であり、顧客満足度を大きく左右する工程です。
バーコードやQRコードを活用した自動検品システムを導入することで、ヒューマンエラーを大幅に削減することができます。また、検品結果をシステムと連携させることで、在庫情報の正確性も高まり、返品やクレーム対応の効率化にもつながります。
梱包・出荷
出荷検品を終えた商品は、破損防止や輸送効率を考慮した適切な梱包を行ないます。個装・内装・外装を使い分けることで、商品を安全に輸送し、顧客に最適な状態で届けることができます。
また、配送先ごとにラベルを付与し、トラックやコンテナへの積み込みを効率化します。近年は、環境配慮型資材の活用や過剰包装削減の取り組みも進んでおり、コスト削減とサステナビリティの両立が求められています。
配送
最後に、顧客や取引先に商品を届ける「配送」の工程です。配送の品質は、顧客満足度を大きく左右する重要なポイントです。即日配送や時間指定、置き配など、多様化するニーズに対応するためには、配送業者との連携が欠かせません。
また、リアルタイム追跡システムの導入により、配送状況を可視化し、遅延やトラブル発生時の迅速な対応が可能になります。EC需要の増加でラストワンマイル配送が課題となる中、効率的な配送体制の整備は競争力強化に直結すると言えます。
高品質な物流業務を提供するメリット
物流業務は各工程で構成されていますが、それぞれの工程の質が高めることで、多くのメリットがあります。ここでは、そのメリットをいくつかご紹介します。
顧客満足度の向上
物流の品質は、顧客体験を大きく左右します。正確で迅速な配送が実現できれば、顧客からの信頼を得やすくなり、リピート購入やブランドロイヤリティの向上につながります。
特にEC市場では「早く届く」「破損がない」「指定時間通りに受け取れる」という要素が重要です。高品質な物流は、クレームや返品の発生率を低下させるだけでなく、顧客からの高評価の獲得にも寄与します。
これらの要素は、企業全体の売上拡大や市場競争力の向上にも直結します。
取引先との長期パートナー構築
高品質な物流体制は、取引先との信頼関係を強化するポイントでもあります。安定した納期遵守、正確な在庫管理、品質の高い輸送は、取引先にとって大きな安心材料となります。結果的に、長期的なビジネスパートナーとしての関係が築かれ、優先的な発注や共同開発などのビジネスチャンスにもつながります。
また、取引先からの評価が高まることで、競合との差別化を図ることもできます。
(効率化・最適化による)コスト削減
物流品質の向上は、一見コスト増加につながるように見えますが、長期的には大きなコスト削減をもたらします。具体的には、誤出荷や返品対応の削減、在庫過多や欠品による機会損失の防止、倉庫オペレーションの効率化などが挙げられます。
また、配送ルートの最適化や積載効率の改善により、輸送コストを削減することも可能です。加えて、システム化や自動化の導入により、人件費削減と業務スピード向上を同時に実現できる点も大きなメリットです。
物流業務の効率化
高品質な物流は、単に配送精度を高めるだけではなく、業務全体の効率化を推進します。WMS(倉庫管理システム)やTMS(輸送管理システム)などを導入すれば、在庫管理やピッキングの精度を高められると同時に、作業時間の短縮を実現できます。
また、データを活用した需要予測や配送ルートの最適化により、必要最小限のリソースで最大の成果を出すことも可能です。効率的な物流体制は、スタッフの負担軽減にもつながり、結果的に現場の安定稼働を支えます。
繁忙期・緊急時の対応力強化
繁忙期や予期せぬ需要増加時にこそ、物流体制の真価が問われます。高品質な物流体制を構築しておけば、需要変動に柔軟に対応でき、在庫切れや出荷遅延などのリスクを最小限に抑えることができます。
特にECや食品など需要変動が大きい業界では、安定的な供給を維持できるかどうかが競争力の差につながります。
強固な物流体制を構築するポイント
作業オペレーションを整備する
高品質な物流を実現するためには、まず現場の作業オペレーションを整備することが重要です。入荷検品から出荷までの一連の業務手順を明確にし、マニュアル化することで、スタッフ間の作業品質を均一化できます。
また、KPI(重要業績評価指標)を設定し、ピッキングの精度や出荷のリードタイムなどを可視化することで、継続的な改善活動につなげられます。標準化と見える化の両立により、属人化を防ぐことができるので、安定した品質を実現しやすくなります。
WMS・自動化システムの導入
倉庫管理システム(WMS)や輸送管理システム(TMS)を導入することで、物流現場の生産性は大幅に向上します。WMSは在庫の正確な位置情報を管理し、効率的なピッキングを可能にする一方、TMSは最適な配送ルートの算出やコスト削減に貢献します。
また、ピッキングロボットや自動搬送車(AGV)を活用すれば、人手不足の解消や作業ミス防止にもつながります。近年はクラウド型システムも普及しているので、導入コストを抑えながら効率化を進めることもできます。
在庫管理の精度向上、適正在庫維持
物流品質を高める上で欠かせないのが、在庫管理の精度向上です。正確な在庫情報をリアルタイムで把握すると、過剰在庫や欠品を防ぎやすくなります。結果、キャッシュフローの健全化につながります。需要予測データや販売動向を分析し、適正在庫の維持に努めましょう。
また、定期的な棚卸しの実施や、WMSとの連携により、在庫差異の発生を最小限に抑えられます。精度の高い在庫管理は、安定した供給体制の構築に直結します。
業務委託戦略(3PLの選択肢)
物流業務を外部に委託する「3PL(サードパーティ・ロジスティクス)」の活用も、効率的な体制構築の有力な選択肢となります。自社で倉庫や配送網を整備するには多大なコストと時間がかかりますが、3PLを利用することで、スピーディかつ柔軟に物流リソースを確保できます。
また、繁忙期や突発的な需要増加にも対応しやすくなり、EC市場での競争力強化につながります。適切な3PL業者を選定する際は、サービス範囲や対応スピード、システム連携性を重視することがポイントです。
DX推進と現場改善・業務負担軽減
物流DXの推進により、業務効率化と現場負担軽減を同時に実現できます。AIによる需要予測、IoTによるリアルタイム在庫監視、RPAによる業務自動化など、最新技術の活用は現場の人手不足解消にもつながります。
また、データ活用による業務改善は、作業者への負担軽減とミス削減を実現し、より高品質なサービス提供を可能とします。DXを戦略的に推進し、企業全体の競争力を強化しましょう。
まとめ
物流業務は、単なる「モノの移動」ではなく、在庫管理・輸送・加工・情報管理など、多岐にわたるプロセスが連携して成り立っています。効率的な物流体制を構築することで、コスト削減や業務効率化はもちろん、顧客満足度や取引先との信頼関係強化にもつながります。ぜひ、物流業務の流れを知り、各工程で質の高い作業を行なえる体制を構築していきましょう。