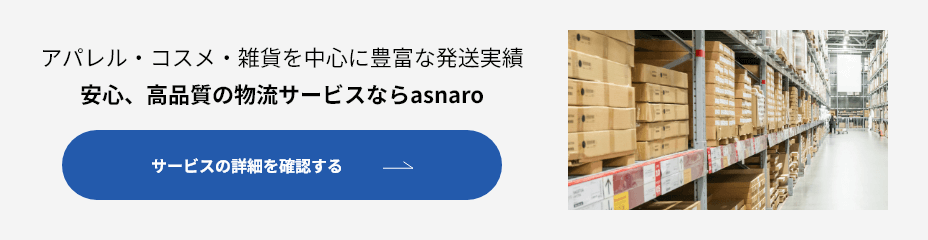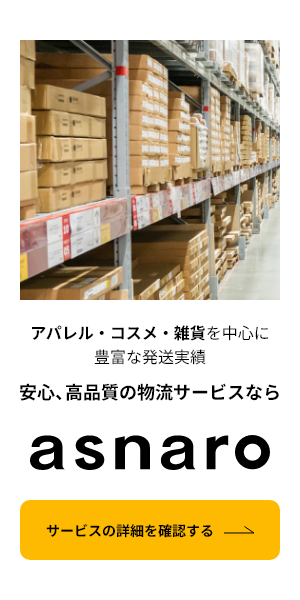物流代行とは?仕組みやメリット、業者選びのポイントを解説

物流業務の課題を解決するために、「物流代行」を活用する企業が増えています。
物流代行は、商品の入荷や保管、梱包、発送、返品対応などの業務を、専門の業者へ委託するサービスのことです。
本記事では、物流代行の仕組みや、利用する際のメリット・デメリット、業者選びのポイントを解説します。
物流業務の外部委託を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
物流代行とは?
物流代行とは、商品の保管から梱包、発送などの物流業務を、外部の専門業者に委託するサービスです。
ネットショップなどを運営していると、扱う商品が増えるにつれて在庫管理や発送作業が煩雑になりがちです。こうしたバックヤード業務に追われ、本来力を入れるべき商品企画や顧客対応に時間を割けない、と感じる事業者も少なくないでしょう。
物流代行を活用すると、手間のかかる作業を専門家に一任できます。物流のプロが業務を担うことで、梱包の質や配送スピードが安定し、顧客満足度の向上につなげられます。
結果、事業者は自社の強みであるコア業務に集中できるようになります。
物流代行と3PLの違い
物流代行と似た言葉に「3PL(サードパーティ・ロジスティクス)」があります。両者は業務の範囲に違いがあり、以下のように整理されます。
| 物流代行 | 3PL | |
|---|---|---|
| 主な役割 | 物流実務の代行(保管、梱包、発送など) | 物流全体の設計・提案・実行 |
| 目的 | 業務負担の軽減、作業の効率化 | 物流の仕組み全体の改善、コスト削減 |
| 関わり方 | 物流作業の委託先 | 物流戦略の立案から関わるサポート役 |
上記の表のとおり、物流代行は、日々の商品の保管や発送作業を外部委託するサービスです。
一方の3PLは、物流作業を代行するだけではありません。「どうすれば全体の物流コストを下げられるか」「どこに在庫拠点を持つのが効率的か」などの経営視点での課題に対し、物流戦略の立案から関与します。
つまり、物流業務を効率化したい場合は物流代行、物流システム全体を見直して経営改善につなげたい場合は3PL、というように目的によって選択肢が変わります。
物流代行を利用するメリット
物流代行には主に以下のメリットがあります。
- コスト削減
- 業務効率化
- 需要変動に対応できる
ひとつずつ解説します。
コスト削減を期待できる
物流代行の最大のメリットはコスト削減につなげられる点です。
自社で倉庫やスタッフを抱えると、物量の少ない閑散期でも家賃や人件費を支払い続けなければなりません。
しかし、物流代行なら、利用した分だけ費用を支払う料金体系が多いため、閑散期に無駄なコストを抱えるリスクを減らせます。
さらに、専門業者は多くの荷物をまとめて扱うことで、配送料金や梱包材を安く仕入れています。コスト削減だけでなく、プロの管理によって発送ミスが減り、それに伴う損失を防げるのも大きな利点と言えます。
業務効率化を実現できる
物流代行を利用することで、本来注力すべき業務に集中でき、事業全体の生産性を高めることができます。
物流業務には、商品の保管から発送まで多くの工程があり、自社で全てを担うと多くの時間や人手を費やします。この状況が、企業の成長を支える商品企画や販売促進などの活動の妨げになることも少なくありません。
物流代行を活用し、これらの作業を専門業者に任せれば、社内スタッフは本来の業務に専念する時間を確保できます。
さらに、専門業者の持つ在庫管理システムなどを活用することで、より正確で迅速な出荷が実現し、顧客満足度の向上にもつなげられるでしょう。
需要変動に対応できる
事業の成長段階や需要の波に合わせて、物流の規模を調整できる点も物流代行のメリットです。
EC事業では、セールや季節のイベントで注文が一時的に殺到することも少なくありません。自社で物流を管理している場合、この急な物量増に対応するための人員や倉庫スペースの確保が、課題となることがあります。
そこで物流代行を利用すれば、こうした物量の変動に応じて業者側がリソースを調整可能です。これにより、事業者は急な出荷増に慌てることなく、販売の機会を逃さずに済みます。
このように物流面の不安が解消されることで、企業は事業拡大や新商品の販売に、集中して取り組めるようになります。
物流代行のデメリット
メリットの多い物流代行ですが、いくつか注意すべき点もあります。ここからは、物流代行のデメリットについて解説します。
毎月、固定でコストがかかる
物流代行では、出荷量にかかわらず毎月一定の固定費がかかることがあり、事業規模によってはコストが割高になります。
多くの代行業者が、基本料金や最低利用料金を設定しているため、たとえ発送が少ない月でもこの固定費は発生します。
たとえば、小規模なECサイトや、たまにしか売れない商品を扱う場合、この固定費が利益を上回ってしまうことも考えられます。そのため、契約前には自社の出荷量をもとに料金を試算し、費用対効果を検討することが大切です。
情報共有やシステム連携の手間が発生する
システム連携やその準備に手間がかかる点も物流代行のデメリットとして挙げられます。
在庫数や出荷指示、返品状況などをリアルタイムで連携しないと、認識のズレからトラブルが生まれやすくなります。たとえば、自社の受注管理システム(OMS)と業者の倉庫管理システム(WMS)がうまく連携できないと、在庫が合わなくなったり発送が遅れたりして、顧客からの信頼を失いかねません。
物流業務を円滑に委託するには、導入前のシステム整備や連携テストなどの、入念な準備が必要になります。
業者選びに失敗すると品質リスクに問題が出てくる
委託する業者によってサービスの質は異なるため、選定を誤ると、発送ミスや遅延などのトラブルが増え、自社の信頼を損なう可能性があります。
物流は、お客様に商品をお届けする最終工程であり、ここでの失敗はすべて自社の責任として受け取られてしまうためです。
商品の梱包が雑で中身が破損していたり、指定日時に届かなかったりすれば、お客様に悪い印象を与えてしまう場合があります。
物流サービスの品質は自社の評価につながるため、業者選びの失敗は大きな事業リスクになるのです。
物流代行業務の流れ
お客様からの注文後、商品がどのように届けられるか、物流代行業務の流れを見ていきましょう。
入荷
商品が倉庫に届き、在庫として受け入れる「入荷」は、物流業務の最初の工程です。ここで発注内容と実際の商品が一致しているかを正確に確認しないと、在庫のズレや誤出荷の原因となります。
物流倉庫では、商品が届くとまず数量や品目に間違いがないかを確認し、システムに在庫として登録することで、販売可能な状態になります。このように、正確な入荷処理が、信頼性の高い物流サービスにつなげられます。
検品・ロケーション
「検品・ロケーション管理」は、商品の品質を保ち、倉庫内作業を効率化するための工程です。
不良品がお客様の元に届くのを防ぐと同時に、どこに何があるかを正確に管理することで、ピッキング作業を迅速に進めることが可能です。
入荷した商品に傷などがないかを確認し、問題がなければ倉庫内の決められた棚へ保管します。この丁寧な検品と整理整頓が、作業全体のスピードと正確性につながります。
在庫管理
「在庫管理」とは、商品の数や状態を正確に把握し、いつでも適切な量を保つことを指します。これは販売機会の損失を防ぐ、物流業務の中心ともいえる業務です。在庫がデータ上の数字と合っていないと、販売機会を逃したり、逆に不要な在庫を抱え続けたりします。
多くの物流代行業者では、倉庫管理システム(WMS)を用いて在庫をリアルタイムで管理し、ECサイトの表示と実際の在庫数を正確に連動させます。この正確な在庫管理が、欠品や過剰在庫のリスクを減らし、安定した事業運営を支えるのです。
ピッキング・出荷検品
「ピッキング」とは注文リストに沿って倉庫から商品を集め、「出荷検品」とは集めた商品が正しいか発送前に確認する作業です。これらは、お客様からの注文通りに、正確な商品を届けるための最終確認の工程といえます。
ここでのミスは「誤出荷」となる可能性があり、クレームや信頼の低下につながります。そのため、発送前には商品や数量が注文内容と一致しているか、入念に確認し、誤出荷を防ぐことが大切です。
梱包・発送
「梱包」とは商品を段ボールなどに入れて保護する作業、「発送」とはその荷物を配送業者に引き渡す作業です。これらは商品を安全にお届けすると同時に、企業のブランドイメージを伝える役割を担います。
きれいな梱包材を選んだり、感謝のメッセージを添えたりするなど、丁寧な梱包を心がけることで、顧客満足度の向上につなげることが可能です。
必要に応じて返品対応
「返品対応」とは、お客様から返送された商品を受け取り、検品や返金、在庫への再登録などを行なう一連の作業です。
返品対応は、万が一の際に顧客満足度を維持するための重要なアフターサービスで、対応が迅速かつ丁寧であれば、お客様の信頼感も高まります。
物流代行の費用相場
物流代行の費用相場は以下のとおりです。
| 項目 | 料金相場 | 単位・備考 |
|---|---|---|
| 基本料金 | 30,000~50,000円 | 月額 |
| 入庫料金 | 10~30円 | 商品1つあたり |
| 保管料金 | 2,500~7,000円 | 1坪あたり(月額) |
| ピッキング・検品料金 | 10~30円 | 商品1つあたり |
| 梱包料金 | 100~400円 | 商品1つあたり |
| 梱包資材料金 | 30~200円 | 1梱包あたり |
| 発送料金 | 400~800円 | 1発送あたり |
物流代行の料金体系は大きく分けて「初期費用」「月額固定費」「従量課金型」の3種類があります。
初期費用はシステム設定や倉庫立ち上げにかかるコストです。月額固定費は、出荷量にかかわらず毎月一定額を支払う料金体系のことです。毎月の費用が一定のため、予算が立てやすく、月々の出荷量が安定している企業にとって管理しやすい料金体系といえます。
一方、従量課金型は出荷件数や在庫量に応じて料金が変動するため、シーズンやキャンペーン時など出荷量に波がある企業に向いています。
自社の出荷規模や商品の特性に合わせて、適切な料金体系を選択することが重要です。
物流代行のコストを抑えるポイント
物流代行のコストを抑えるには、
「発送件数」
「倉庫の立地」
「梱包資材」
の3点を見直すことが重要です。
これらは月々の費用に大きく影響する要素であり、自社の事業特性に合わせて検討することで、無駄な出費を減らせます。
たとえば、発送量の季節変動が大きい場合は、閑散期と繁忙期でプランを見直すと固定費を削減できる可能性があります。
また、主要な顧客エリアに近い倉庫を持つ業者を選べば、一件あたりの配送料もおさえられるでしょう。梱包材を業者が提供するものに切り替えるのも、コスト削減のための有効な手段のひとつです。
物流代行業者の選び方
ここからは、物流代行業者の選び方について解説します。それぞれのポイントを把握して、複数の業者を比較検討し、自社に合う代行業者を見つけましょう。
自社の出荷規模に合うか
物流代行業者を選ぶ際は、自社の出荷量や繁閑の差など、事業の規模に合った業者を選びましょう。
業者によって得意とする物量が異なり、ミスマッチが起きるとコスト面でも運営面でも問題が生じるからです。
たとえば、小規模な事業者が大規模向け業者に頼むと、最低利用料金によって費用が割高になる可能性があります。大規模な事業者が小規模向け業者を選ぶと、繁忙期に発送が追いつかなくなることも考えられます。
まずは自社の月間出荷量や繁閑の差を把握し、それに適した規模を得意とする業者を探しましょう。
その業者が得意な業界・商品カテゴリーは何か
物流代行業者を選ぶ際は、自社が扱う商品の分野で、取り扱い実績が豊富な業者を選ぶことが大切です。
もし、専門外の業者に依頼してしまった場合、品質の低下やトラブルを招くことがあります。
アパレルならサイズや色の管理、食品なら温度や賞味期限の管理が必要です。また、化粧品のように厳密な品質管理が求められる商材もあります。
業者ごとの得意分野をよく調べ、自社の商品に適したノウハウを持つ業者を選ぶことで、商品特有の品質管理やクレーム対応への心配が減り、本来の業務に集中できるでしょう。
在庫管理システムの連携はできるか
物流代行業者を選ぶ際は、自社が利用する販売サイトや受注管理システムと、業者の倉庫システムがスムーズに連携できるかを確認しましょう。
システム間のデータ連携がうまくいかないと、在庫数のズレや発送遅れなどのトラブルにつながる可能性があります。
自社のECサイトと業者の倉庫管理システム(WMS)を連携させると、在庫状況を正確にリアルタイムで管理できます。商品がひとつ売れると、その情報が即座にシステムへ反映され、ECサイト上の在庫表示が自動で更新されるため、「売り逃し」や「空売り」を防げるでしょう。
さらに、Amazonや楽天など複数のチャネルで販売している場合、この連携はとくに重要になります。あるサイトで商品が売れると、すべての販売サイトの在庫数が同時に自動更新されるため、チャネルごとの在庫調整の手間が不要になります。
契約前には、API連携の可否やデータの更新頻度など、具体的な連携方法について詳しく確認しておくことが大切です。
サポート体制は充実しているか
物流代行業者を選ぶ際は、日々のやり取りのしやすさはもちろん、トラブル発生時の対応力や、業務改善への姿勢など、サポート体制の充実度を確認することが大切です。
物流業務では予期せぬトラブルが起こることもあり、その際の対応の速さや正確さが、事業に影響を与える可能性があります。
急な出荷増への対応や配送遅延が起きた際に、すぐに連絡が取れて的確な対応をしてくれるかは、確認すべき重要なポイントです。
また、専任の担当者がつき、問い合わせへの返信が早い業者であれば、日々のやり取りがスムーズになり、業務も円滑に進みます。定期的なレポートや改善提案をくれる業者であれば、さらなる物流業務の効率化も可能です。
契約前に、こうしたサポートの具体的な範囲と内容を確認しておくことで、委託後のミスマッチを防げるでしょう。
まとめ
物流代行は、商品の入荷から保管、梱包、発送、返品対応までを専門業者に委託できるサービスで、業務効率化とコスト削減を実現できます。
一方で、固定費や情報共有の手間、業者選びの難しさなどの課題もあります。自社の出荷規模や商品特性に合わせて適切な業者を選定し、物流体制を整備することが重要なポイントです。
まずは複数の業者に相談し、比較検討することをおすすめします。