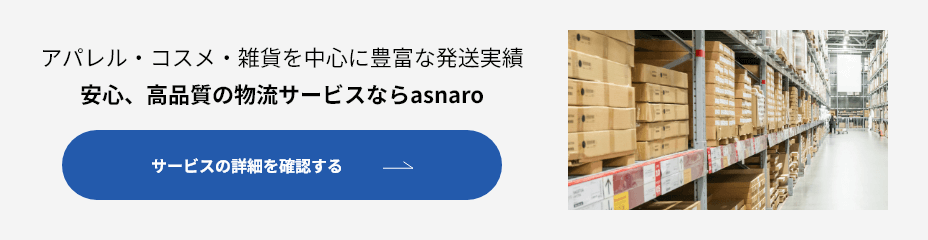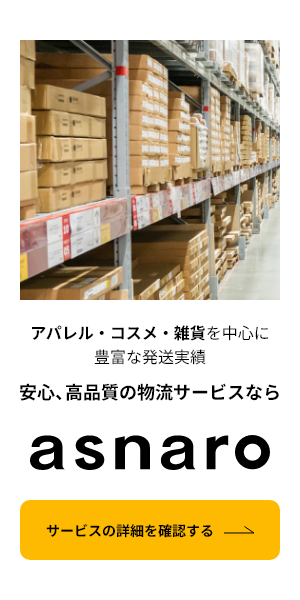在庫管理とは?基本の考え方や管理のポイントを解説

「在庫が多すぎてキャッシュフローが厳しい」
「売れ筋商品が欠品し、チャンスを逃してしまった」
そんな悩みを抱えるEC運営者は少なくありません。在庫は、抱えすぎても不足しても、業務全体の効率や収益に影響を与えます。だからこそ、現場に合ったルールや仕組みを整え、日々の管理に一貫性をもたせることが重要です。
この記事では、在庫管理の基本的な考え方から、バーコードやITシステムを取り入れた効率化の手法まで、実際に活用できる方法を解説します。日々の業務負担を軽減しながら、販売機会を逃さない仕組みづくりに、本記事の内容を役立ててください。
目次
在庫管理とは何か?
EC事業を安定的に成長させるには、売上や広告戦略だけでなく、バックヤードの仕組みづくりも欠かせません。その中でも特に重要となるのが在庫管理です。この章では、在庫管理の基本的な役割や重要性について解説します。
在庫管理とは?
在庫管理とは、企業が保有する商品や原材料、部品などの在庫状況を正確に把握し、必要に応じて効率的に運用していくための業務を指します。数量や保管場所、入出庫の履歴を管理し、必要なときに必要な分だけ在庫を確保できる状態を保つことが目的です。
特にEC事業では、注文から出荷までの流れを滞りなく進めるうえで、在庫管理は欠かせません。過剰在庫や欠品を防ぐために、商品の動きをリアルタイムで把握し、常に最新の状態に保つことが求められます。
在庫の見える化や数量の正確な把握、そして適切なタイミングでの補充判断。この3点を軸にした在庫管理を行なうことで、キャッシュフローが健全化し、業務効率の改善にもつながります。
なぜ在庫管理が重要なのか?
在庫管理が重要な理由は、事業の収益性と顧客満足度に直結するためです。適切な在庫管理を行なわないと、さまざまな問題が発生します。
まず、過剰在庫は資金の固定化を招きます。売れない商品が倉庫に眠っていると、その分の仕入れ資金が回収できず、キャッシュフローが悪化する可能性もあります。一方で、在庫不足は販売機会の損失につながり、顧客の信頼を失う原因にもなりかねません。
また、在庫管理が不適切だと、保管スペースの無駄遣いや管理コストの増大を引き起こします。商品の劣化や紛失のリスクも高まり、結果として利益を圧迫することになるでしょう。
このような状況は、顧客からのクレームや悪い評価につながり、ビジネスの成長を妨げる要因となります。効果的な在庫管理の方法を実践することで、これらの課題を解決し、安定した運営が可能になるのです。
在庫管理の基本的な考え方
在庫管理を効率よく行なうには、基礎となる考え方を正しく理解しておくことが大切です。ただ商品を倉庫に保管するのではなく、資金の使い方と顧客対応の両面を最適化する戦略的な管理が求められます。この章では、EC運営において重要となる3つの基本的な考え方を解説します。
適正在庫を把握する
適正在庫とは、需要に応えつつ、在庫の持ちすぎによる資金の圧迫を防ぐ最適な在庫数のことです。商品が多すぎると保管コストがかさみ、キャッシュフローを悪化させます。逆に少なすぎると販売の機会を逃し、顧客対応にも支障が出ます。
EC事業では、適正在庫の維持が安定した運営につながります。適正在庫を求める計算式は「平均出荷量×(発注リードタイム+発注間隔)+安全在庫」です。
たとえば、月に100個売れる商品で納品までに7日かかる場合、1日あたり約3.3個の出荷として23個が必要です。ここに急な注文増に備えた10個の安全在庫を加え、適正在庫は33個程度となります。
在庫数を数値で管理することで、過不足のない効率的な運用が可能になります。
在庫回転率を確認する
在庫回転率は、一定期間内に在庫がどれだけ入れ替わったかを示す指標です。「売上原価 ÷ 平均在庫金額」で求められます。数値が高いほど、在庫がスムーズに流れていることを意味します。
たとえば、年間の売上原価が1,200万円、平均在庫が100万円であれば、回転率は12回です。これは、月に1回在庫が入れ替わっている計算になります。アパレルなら年4〜6回、食品なら年10~15回が一般的な目安です。
回転率が低いと在庫が滞留し、保管コストや廃棄リスクが高まります。一方で、高すぎると在庫が不足し、販売機会を逃すおそれがあります。商品ごとの特性を踏まえて回転率を確認し、適切な在庫水準を維持することが重要です。
発注点とリードタイムの管理
発注点は、在庫が一定数を下回ったときに新たな発注をかける基準です。「平均出荷量 × リードタイム + 安全在庫」で算出できます。リードタイムは、発注から商品が届くまでの期間を指し、仕入れ先や物流条件によって異なります。
たとえば、1日10個売れる商品でリードタイムが5日、安全在庫を20個とした場合、発注点は70個です。在庫が70個を下回った時点で発注すれば、欠品を防げます。
ただし、季節変動やキャンペーンなどによる需要の波も加味する必要があります。販売データを分析し、時期ごとの需要パターンを把握することで、より精度の高い発注管理が可能になります。
在庫管理のポイント
在庫管理の精度を高めるには、現場で実行できる具体的な工夫が欠かせません。この章では、適切な在庫管理をするためのポイントについて解説します。
在庫の見える化を徹底する
在庫がどこに、どれだけあるのかを正確に把握できる状態をつくることが在庫管理の基本です。まずは保管場所を商品ごとに決め、誰が見ても分かる表示を行ないます。入出庫のたびに記録を更新し、リアルタイムで在庫状況を確認できる仕組みを整えましょう。
在庫推移をグラフで可視化したり、回転率に応じて色分けすることで、問題点や改善のヒントも見つけやすくなります。こうした見える化により、過剰在庫や欠品の兆候を早期に捉え、対応スピードを高めることができます。
入出庫管理を正確に行なう
入荷・出荷の記録を正しく残すことは、在庫数の誤差を防ぐことにつながります。バーコードやQRコードを使えば、記録ミスを減らしながら作業の効率も上がります。
検品作業では、納品書との照合や商品の不良確認を行ない、不備があれば即時対応することが必要です。出庫では先入先出(FIFO)の原則を守り、出荷指示書と突き合わせることでピッキングミスを防げます。こうした運用が、在庫差異のない正確な管理につながります。
ロケーション管理で作業効率を向上させる
倉庫内の配置を最適化することで、ピッキングや補充の作業効率が変わります。出荷頻度に応じて商品を配置する「ABC分析」の考え方を活用し、頻繁に動く商品は作業動線の近くに置くのが基本です。
ABC分析とは、商品を重要度や出荷頻度に応じてA・B・Cの3段階に分類する手法です。Aランクには出荷頻度が高く動きの多い商品、Bランクには中程度の動きのある商品、Cランクには出荷頻度が低い商品を振り分けます。これにより、使用頻度の高い商品を入口付近や通路沿いなどアクセスしやすい場所に集約し、無駄な動線や作業時間を削減可能です。
また、ゾーニングの工夫も欠かせません。重い商品は下段、軽い商品は上段に、温度管理が必要な商品は専用エリアに集めるなど、特性に応じた配置が作業の安全性と効率を両立させます。ロケーション番号は体系的に設定し、新人でも迷わず動けるように工夫しましょう。
ABC分析で在庫を分類・優先管理する
ABC分析は、在庫を重要度に応じてグループ分けし、それぞれに適した管理手法を適用することで、限られたリソースを効率的に使うための在庫管理の方法です。売上や利益への貢献度、出荷頻度などを指標として、商品をA・B・Cの3つに分類します。
Aグループには、全体の売上の70〜80%を占める上位20%の商品が該当します。販売への影響が大きいため、欠品を防ぐことが最優先となり、発注頻度を高める、安全在庫を厚めに設定するなど、手厚い在庫管理が求められます。
Bグループは、売上の15〜20%程度を占める中位の商品群です。安定供給は必要ですが、Aほど厳密ではなく、在庫水準の調整でコスト削減も可能です。
Cグループは、売上構成比の残り5〜10%を占める商品群で、在庫回転率が低く、過剰在庫になりやすい傾向があります。このグループの商品については、在庫量を最小限に抑え、保管コストを削減するのが基本方針です。必要に応じて受注発注(受注後に仕入れる運用)への切り替えを検討するとよいでしょう。
ABC分析を導入することで、管理の重点を明確にし、資金や作業時間といったリソースを本当に必要な部分に集中させることができます。
定期的な棚卸を実施する
棚卸は、帳簿上の在庫数と実際の在庫数にズレがないかを定期的に確認し、在庫管理の精度を維持するための作業です。ズレがあれば、その原因を突き止めて早期に対応することで、在庫の信頼性を保つことができます。
実施頻度は、商品特性や在庫回転率に応じて決めるのが一般的です。回転の速い商品や高額商品は月1回、比較的動きの少ない商品は四半期ごとなど、分類に応じて柔軟に設計します。
効率よく棚卸を進めるためには、あらかじめ倉庫内を整理整頓し、ロケーションごとのチェックリストを作成しておくことがポイントです。また、棚卸中の入出庫は原則一時停止し、必要に応じて別途記録を残す体制を整えておきましょう。
差異が発見された場合は、入力ミス、ピッキングミス、紛失・盗難など、複数の可能性を洗い出し、再発防止策を講じることが重要です。棚卸を定期的に実施することで、在庫データの正確性が向上し、発注精度の向上につなげられます。
過剰在庫や欠品を防ぐ
在庫は多すぎても少なすぎても、経営にとってはリスクになります。過剰在庫は資金を圧迫し、欠品は販売機会や顧客信頼の損失につながります。これらを防ぐには、計画的な予測と仕組みづくりが欠かせません。
過剰在庫を防ぐには、需要予測の精度向上が効果的です。過去の販売実績や季節要因、市場トレンドを分析し、適切な発注量を設定します。あわせて、ABC分析を活用し、売れ筋と動きの鈍い商品を明確に区分けしたうえで、在庫水準を最適化しましょう。
欠品対策では、安全在庫の設定と発注点の管理が重要になります。需要のばらつきを軽減するために、リードタイムや標準偏差をもとに安全在庫を計算し、アラート機能付きのシステムで自動的に発注を促す仕組みを整えると、対応漏れを防げます。
さらに、在庫の動きを日次でモニタリングし、急な変動や傾向をいち早く捉えられる体制を整えることも重要です。これらの対策を講じることで、過不足のリスクをおさえることが可能となります
在庫回転率を意識した運用を行なう
在庫回転率は、一定期間内に在庫がどれだけ入れ替わったかを表す指標です。回転率が低ければ在庫が滞留し、高すぎれば欠品のリスクが高まります。
まずは商品カテゴリーごとに目標回転率を設定し、自社にとって適正な水準を把握することから始めましょう。日用品であれば月2回転、季節商品であればシーズン中に2〜3回転を目安に設定されることが一般的です。
低回転の商品については、販促・セット販売・値下げなどを通じて在庫消化を進めます。一方で、回転率が高く品切れが懸念される商品は、発注ロットの見直しや安全在庫の再設定が必要です。
回転率は週次・月次で定期的に確認し、改善サイクル(PDCA)を回すことで、安定した在庫運用とキャッシュフローの改善につながります。
倉庫管理システム(WMS)を導入する
在庫管理の精度と効率を大きく高める手段のひとつが、WMS(Warehouse Management System)の導入です。WMSを活用すれば、入出庫・在庫数・保管場所をリアルタイムで一元管理でき、人的ミスや更新漏れを削減できます。
WMSは、バーコードによる自動記録や発注点アラート、履歴追跡機能により、日々のオペレーションが効率化され、担当者の負担も軽減されます。また、ABC分析や回転率の自動計算など、在庫分析ツールも標準で備わっているものが多く、意思決定にも活用できるでしょう。
WMSの導入には初期費用や月額利用料が発生しますが、作業工数の削減や在庫精度の向上によって、コストに見合う効果を得られる可能性があります。
バーコード・QRコード・RFIDなどの自動化技術を活用する
在庫管理の精度を高めながら作業時間を短縮するには、自動化技術の導入が効果的です。バーコードやQRコードは、入出庫作業を高速かつ正確に行なうための基本ツールとして広く普及しています。
バーコードは読み取り速度に優れ、商品番号や数量の管理に有効です。QRコードはより多くの情報を記録でき、製造日やロット番号、保管条件などの詳細も一括で管理できます。
さらに進化したRFID(無線自動識別)は、箱を開けずに中身を一括スキャンでき、棚卸や検品の時間を短縮できます。導入コストは比較的高めですが、人手不足の解消や業務効率化の観点から、短期間で投資回収を実現している企業もあるようです。
リアルタイムな情報共有体制を整備する
在庫情報をリアルタイムで共有できる環境があれば、営業・購買・物流など各部門が同じデータをもとに行動でき、ミスやロスを防げる可能性があります。特にクラウド型の在庫管理システムは、場所を問わず情報にアクセスでき、在庫切れや二重発注を防ぐのに有効です。
アクセス権限を役割ごとに設定することで、業務効率と情報保全の両立も可能になります。現場スタッフには入力権限、管理者には集計・分析機能を提供するなど、使いやすさを意識した構築がポイントです。
さらに、週次での在庫ミーティングなどを取り入れれば、在庫に関する課題や改善点を部門横断で議論し、継続的な改善につなげることができます。情報共有の文化を根づかせることで、在庫の最適化につなげられるでしょう。
在庫管理の注意点
過剰在庫による資金繰りの悪化
在庫が売れずに倉庫内に滞留している状態は、仕入れに使った資金を回収できないままとなり、資金繰りを圧迫する原因になります。倉庫に眠っている商品は、次の仕入れや運営費に回せない「使えない費用」として残ってしまうためです。
特にEC事業では、トレンドの移り変わりが早く、販売のタイミングを逃すと値下げ対応が必要になることもあります。利益率が下がるだけでなく、保管コストや廃棄リスクも増加します。
こうした状況を避けるには、在庫の回転状況を把握しながら、需要に見合った数量を維持することが重要です。売上データとの連携や需要予測の精度向上を通じて、無駄のない在庫水準を保ちましょう。
在庫不足による販売機会の損失
在庫が足りずに販売のチャンスを逃すケースは、利益だけでなく顧客との関係にも影響を与えます。特に人気商品での欠品は、購入意欲の高い顧客を他社へ流してしまうリスクを伴います。
実際、欠品が発生すると、そのブランドや店舗に対する信頼感が低下しやすく、リピーター離れにつながるおそれがあります。一度離れた顧客を再び獲得するには、販促や広告といった追加コストがかかります。
こうした事態を防ぐためには、安全在庫の設定や発注点の管理が不可欠です。過去の販売傾向や季節変動、キャンペーン時期などを考慮し、適切な数量を先回りして確保する仕組みを構築しましょう。システムによるアラート設定や定期的な在庫分析も有効です。
属人化による業務の非効率化
在庫管理業務が特定のスタッフに偏っている状態は、業務の属人化として大きなリスクとなります。特定の人しか在庫の場所を把握していない、ベテランが休むと出荷が止まる、といった状況が発生しやすくなるのです。
業務が属人化していると、急な休職・退職時に業務が滞るだけでなく、作業者本人への負担が集中しやすくなります。疲労や判断ミスが増えれば、在庫差異や出荷ミスといったトラブルにもつながりかねません。
この問題を解消するには、作業手順の標準化が不可欠です。保管ルールや入出庫の方法、記録の取り方などをマニュアル化し、誰が対応しても同じ精度で業務が行なえる体制を整えましょう。
さらに、担当者を固定せずローテーションを組んだり、定期的に情報共有や研修の場を設けたりすることで、知識の属人化を防ぎ、チーム全体の底上げにもつながります。
在庫管理を効率化するには?
在庫管理を効率化する方法の一つとして、外部の物流倉庫に業務を委託する選択肢があります。事業規模が拡大すると、在庫の量や種類が増え、自社だけでの対応が難しくなるケースも少なくありません。
物流倉庫の多くはWMSを導入しており、在庫状況をリアルタイムで把握できます。温度や湿度の管理が必要な商品や、特殊な保管条件を伴う商品にも対応できるため、取り扱いに制限のある商材にも適しています。
また、外部委託を活用することで、保管スペースの柔軟な調整が可能になる点も大きなメリットです。繁忙期には一時的に在庫量が増えることもありますが、自社倉庫ではその変動に対応しきれない場合もあります。外部倉庫であれば必要に応じて保管容量を拡張でき、在庫の波に合わせた運用がしやすくなるでしょう。
ただし、委託先の選定には注意が必要です。自社の商品特性や配送ニーズ、必要とするサービスレベルを明確にしたうえで、複数の候補を比較検討することが重要です。信頼できる委託先を見つけることで、在庫管理の負担を減らし、本来注力すべき業務に集中できるでしょう。
まとめ
在庫管理は、資金繰りの改善や販売機会の最大化につなげられる重要な業務です。適正在庫の維持と在庫回転率の向上を軸に、効率的な仕組みづくりが求められます。そのためには、在庫の見える化を徹底し、入出庫の記録精度を高めることが基本です。ロケーション管理の整備によって、現場作業の効率化にもつながります。
なお、場合によっては「s-flow」のような販売管理システムを活用するのもおすすめです。s-flowは、株式会社コデックスが提供している販売管理クラウドシステムです。在庫管理、入出金管理、会計連携機能を標準装備した中小企業向けクラウド販売管理システムで、 卸販売・ネット販売・店舗販売の統合管理を実現してくれます。業務に合わせてカスタマイズできるプランも用意されており、販売業務の効率化と事業の成長を実現しやすい点が魅力です。
クラウド販売管理システム s-flow | 株式会社コデックス →
ただし、自社だけでの対応が難しい場合は、物流倉庫への外部委託を検討することもおすすめです。ぜひ本記事を参考にしながら在庫管理の改善を進めてみてください。