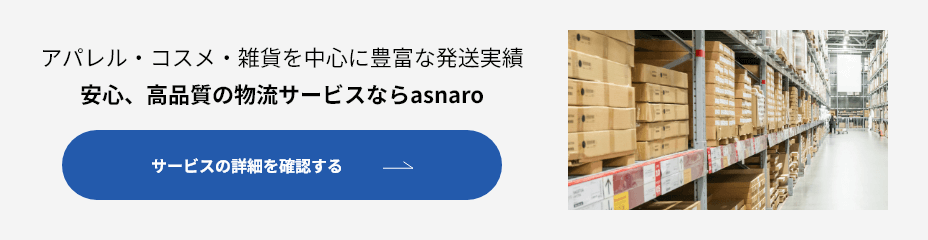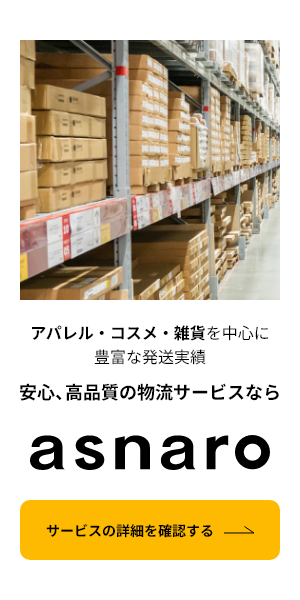物流サービスの品質向上につながる物流改善のポイントとは?

「配送遅延が増えている…」
「物流コストが経営を圧迫している…」
EC市場の拡大とともに、物流の質がそのまま企業の競争力を左右するようになりました。一方で、人手不足や燃料費の高騰など、物流を取り巻く環境は年々厳しくなっています。こうした中でも、現場の工夫次第でコスト削減と顧客満足度の向上を両立させることは可能です。
本記事では、物流改善の方法をわかりやすく解説します。物流改善のメリットや成功事例についてもまとめていますので、業務効率化やコスト削減に取り組みたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
物流改善の必要性
物流体制の見直しは、企業にとって重要な経営課題です。人手不足や燃料費の上昇、労働規制の強化など、業界を取り巻く環境が急速に変化しているためです。
特に、トラックドライバーの高齢化と若年層の担い手不足が深刻化しており、輸送力の維持が難しくなりつつあります。EC需要の拡大によって配送が複雑化し、対応に追われる企業も少なくありません。
こうした課題に対処するには、従来のやり方に固執せず、少ない人員でも回るしくみを整えることが重要です。業務の自動化や手順の見直しにより、効率よく物流を支える体制を整える必要があります。
物流改善のメリット
物流業務を見直すことで、現場の効率化やコスト削減など、さまざまな効果が期待できます。作業時間を短縮するだけでなく、サービス品質の向上や人件費の見直しにもつなげられます。ここでは、物流改善によって得られる主なメリットを見ていきましょう。
業務効率化とサービスの質の向上を期待できる
物流の仕組みを見直すと、作業効率とサービス品質の向上を期待できます。たとえば、倉庫内の商品配置を出荷頻度に応じて再編成すれば、移動距離が短くなり、業務時間の短縮につなげられます。移動が減ることで体力的な負担も軽減され、スタッフには心理的な余裕も生まれます。その余力を活用すれば、納期の問い合わせ対応や、きめ細かい梱包作業にもリソースを割けるようになります。
また、倉庫管理システム(WMS)の活用により、在庫数の把握が正確になり、欠品や過剰在庫のリスクも下がります。作業マニュアルを整備することで、スタッフの習熟度にかかわらず一定の品質を維持できる環境も整います。このような改善の積み重ねが、信頼される物流体制の構築へとつながります。
物流コストの削減につながる
物流改善に取り組むと、輸送費や保管費といったコストの削減が見込めます。配送ルートを見直せば走行距離を短縮でき、燃料費の圧縮につなげられます。複数拠点への納品をまとめれば、車両の稼働効率も高まります。
また、在庫の見直しも有効です。売れ行きの悪い商品を減らし、保管スペースを最小限におさえられれば、倉庫費用の負担も軽くなります。商品を分類する際にはABC分析を活用し、回転率を高める工夫が求められます。
さらに、作業の自動化によって人員を再配置できれば、人件費の削減にもつながります。初期費用は発生しますが、中長期的には費用対効果が期待できます。
物流改善の基本的な考え方
物流現場の課題を解決するには、全体を見通した改善の視点がポイントになります。人員やコストに制約がある中でも、現場に適した方法を選び、効率的に運用できる体制を整えることが求められます。ここでは、押さえておくべき3つのポイントをご紹介します。
作業効率を向上させる
物流現場の作業効率は、業務全体の質やコストに影響します。ピッキングや梱包の工程を見直すだけでも、処理能力の向上につながります。出荷頻度の高い商品を取りやすい場所に配置すれば、移動距離が短くなり、1日の作業件数を増やすことも可能です。こうした取り組みが、物流コストの見直しにつながります。
作業品質を安定させるには、業務手順を明確にすることが必要です。担当者の経験に頼らず、誰が行なっても一定の品質が保たれるように設計しておく必要があります。さらに、ハンディターミナルなどのIT機器を取り入れれば、バーコードを使った検品作業の効率が上がります。人手による確認と比べて作業時間が短縮され、誤出荷の防止にも役立ちます。
ヒューマンエラーを削減する
物流業務では、ピッキングの取り間違いや誤配送といった人為的なミスが、サービス品質の低下につながります。人が関わる以上、完全になくすことはできませんが、現場の工夫で発生頻度を抑えることは可能です。
まず、視認性に配慮した作業環境を整えることがポイントです。たとえば、似た商品を離れた棚に置いたり、ラベルの文字を大きく表示したりすると、作業ミスの防止につながります。照明を明るくするだけでも作業の正確さが向上します。
また、バーコードによる検品やダブルチェック体制の導入によって、出荷前の確認精度を高められます。加えて、長時間の連続作業が集中力を下げる要因になるため、適度な休憩時間の確保も必要です。ミスが起きた場合には、原因を洗い出し、再発を防ぐ取り組みを継続的に行なうことも求められます。改善を積み重ねることで、より信頼性の高い物流体制が築けます。
3M(ムリ・ムダ・ムラ)を排除する
物流現場で効率的な運営を目指すには、「ムリ・ムダ・ムラ」の3Mをなくす取り組みが欠かせません。
- ムリ
- 作業者や設備に過度な負担がかかる状態を指します。重量物を手作業で運ぶ作業や、慢性的な人手不足による長時間労働がよく見られるケースです。
- ムダ
- 作業の付加価値を生まない時間や動きが含まれます。商品の保管が過剰になるとスペースを圧迫し、倉庫内で目的の品を探す手間も増えがちです。さらに、トラックの積み下ろしを待つ時間も生産性を下げる要因になります。
- ムラ
- 作業量や品質に生じるばらつきのことです。たとえば、曜日や天候によって出荷件数が大きく変動するケースや、担当者ごとに作業スピードが安定しない状況などが含まれます。
こうした非効率の要因は、作業時間や移動経路を計測すれば明確になります。得られたデータをもとに、作業量の均一化や機器の自動化、倉庫内レイアウトの調整などを進めていくと、継続的な改善につながります。
物流改善の主な手法
物流業務をより良くするためには、自社の実情に合った具体策を選び、計画的に導入することが求められます。ここでは、多くの現場で成果が報告されている代表的な5つの改善手法を取り上げます。
作業工程を見える化する
物流現場の改善を進めるには、まず作業工程を見える化する取り組みが効果的です。各作業にかかる時間や手順を記録・分析すれば、処理の停滞や無駄な動きが発見しやすくなります。
たとえば、ピッキング作業の様子を撮影して作業員の移動経路を可視化すると、遠回りや無駄な往復が明らかになります。作業動線を見直した結果、運搬距離が約25%短縮できたケースもあるようです。
ストップウォッチやタイムスタディを使って所要時間を測定し、標準作業時間を設定すれば、生産性の比較や評価も行ないやすくなります。
こうしたデータを活用すれば、どの改善策から手をつけるかを判断しやすくなります。短期間で効果が見込める改善から取り組むことで、現場全体の意識向上にもつながるでしょう。
作業マニュアルを整備する
物流改善を進めるうえで、作業マニュアルの整備は品質の安定に貢献します。マニュアルを整備することで、業務が特定の担当者に依存している状態を解消し、誰でも同じ水準の作業を実行できるようになります。
マニュアルには、写真や図解を取り入れることが効果的です。梱包手順や機器の操作方法など、文章だけでは伝わりにくい作業も視覚的な情報を加えることで理解しやすくなります。
ただし、マニュアルは一度作ったら終わりではありません。現場の声を取り入れながら定期的に見直し、季節商品や新ルールなどの変更点を反映させることで、実用的な状態を保てます。
加えて、マニュアルのデジタル化も選択肢のひとつです。タブレットで作業中に確認できれば、作業効率と対応力の向上につながります。こうした取り組みは、ミスの削減と品質維持の両面で役立ちます。
スタッフ教育を徹底して実施する
物流改善を進めるには、現場スタッフの理解とスキルの習得が欠かせません。どれだけ優れた仕組みを整えても、それを正しく運用できなければ効果は出にくくなります。
教育に取り組む際は、その作業がなぜ必要なのか、業務全体にどう影響するのかといった背景まで伝えることが重要です。業務の意味を理解したうえで取り組むスタッフは、主体的に行動しやすくなります。
また、日常業務の中で行なうOJT(On-the-Job Training)も効果的です。これは、実際の作業現場で業務を通じて指導を行なう教育手法で、ベテランが新人に付き添いながら作業の流れや判断のコツを伝えていきます。
加えて、改善提案を吸い上げる仕組みも整えることも重要なポイントです。日々の業務に向き合うスタッフだからこそ、業務のムリやムダに気づく場面は多くあります。こうした現場の声を反映すれば、より実態に即した改善が進みやすくなります。
自動化技術(マテリアルハンドリング機器など)を導入する
物流業務の効率化を進めるうえで、自動化の導入は有力な選択肢のひとつです。無人搬送車(AGV)や自動倉庫システムなどのマテリアルハンドリング機器を活用すれば、重量物の運搬や単純な繰り返し作業から作業者の負担を軽減できます。
人手に頼らず処理できる工程が増えることで、限られた人材をより戦略的な業務へ振り分ける余地も生まれます。自動仕分け機やバーコードスキャンの自動化技術は、ヒューマンエラーの低減にも役立ちます。
導入には一定のコストがかかりますが、繰り返し作業や危険を伴う業務から段階的に自動化を進めることで、費用対効果を着実に引き出すことが可能です。
デジタル化によって業務効率化やペーパーレス化を実現する
紙に頼った管理体制から脱却し、システムを用いたデジタル管理へ移行する企業が増えています。WMS(倉庫管理システム)を導入すれば、在庫数や保管場所がリアルタイムで把握できるようになり、欠品や在庫過多といったトラブルを未然に防ぎやすくなります。
配送管理の分野でも、ドライバーの現在地や納品状況をリアルタイムで確認できる仕組みが整えば、問い合わせ対応のスピードが上がり、顧客対応の質も向上します。作業指示書などの帳票を電子化することで、伝達ミスや更新の遅れを防ぎやすくなるのも利点です。
物流改善の成功事例
物流改善への取り組みは、理論だけでなく実践から学ぶことが重要です。実際に成果を上げている企業は、どのような施策を実施し、どんな工夫をしているのでしょうか。
ここでは、国土交通省が推進する「ホワイト物流」運動に賛同する企業の具体的な取り組みをはじめ、さまざまな業界で実施されている物流改善の成功事例を見ていきます。
「ホワイト物流」推進運動における賛同企業の取り組み
「ホワイト物流」推進運動は、国土交通省が主導する取り組みで、トラックドライバーの労働環境を見直し、持続可能な物流体制を目指すものです。2025年3月時点で、約3,140社の企業が賛同しています。
賛同企業のなかには、待機時間の削減や荷役作業の効率化に取り組む例が増えています。たとえば、イオンは予約システムを導入することで、ドライバーの拘束時間を減らす工夫を進めています。また、花王ではパレット輸送を標準化し、荷役作業のばらつきを抑える取り組みを実施中です。
このほか、アサヒビールとキリンビールが北海道で共同配送を実施し、輸送効率の改善を図っています。CO₂排出量の抑制や輸送コストの縮小といった効果も期待されており、企業連携による物流改革の可能性が広がっています。
改善事例から得られる効果的な進め方
上記の事例から物流改善の効果的な進め方は、主に以下の4つです。
- 配送リードタイムや在庫回転率など、改善目標を数値で設定する
- 影響範囲の小さい部門から段階的に導入を進める
- 現場スタッフの意見を吸い上げる仕組みをつくる
- 投資回収の見込みが立つ施策から優先的に取り組む
これらの実践例に共通しているのは、現場に無理を強いるのではなく、着実に成果を積み上げている点です。改善の方向性を明確にし、段階的な導入で効果を確かめながら広げていく方法は、現場の混乱を抑えつつ安定した改革を進められます。
また、日々の業務に最も詳しいスタッフの声を取り入れることで、実態に合った改善が可能になります。費用対効果の面でも、早期に投資回収が見込める施策から取りかかることで、経営層の理解が得やすく、継続的な取り組みにもつながります。
まとめ
物流業界は、慢性的な人手不足や燃料費高騰を受け、安定した運営が難しくなっています。しかし、現場に合った改善策を導入すれば、業務の効率化とコストの圧縮は十分に可能です。作業工程の見える化やマニュアルの整備、スタッフ教育の仕組みづくりを進めることで、現場の安定性が高まります。
また、自動化設備やデジタルツールの活用によって、ムリ・ムダ・ムラといった非効率な要素の排除や、ヒューマンエラーの削減にもつながります。「ホワイト物流」推進運動で見られるように、実際の改善事例からも効果が伺えます。EC市場の拡大と顧客ニーズの多様化に対応するためにも物流課題がある方は、ぜひその見直しを図ってみましょう。