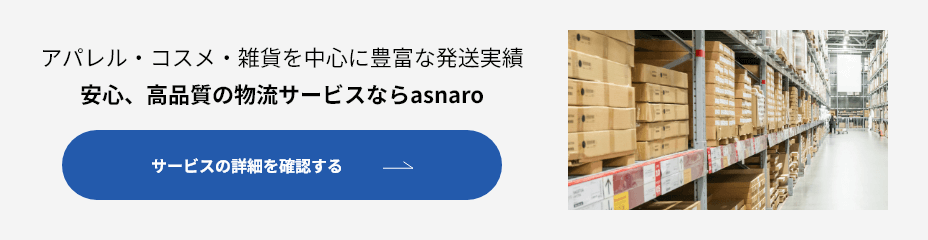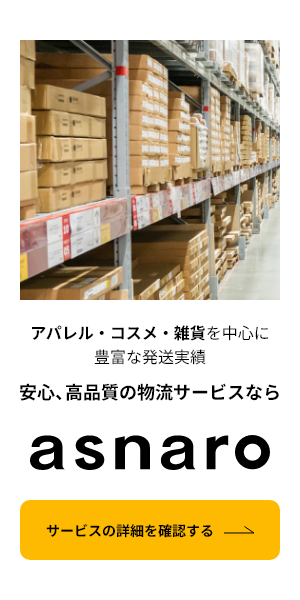冷蔵倉庫とは?温度基準や分類、設備の選び方を解説

冷蔵倉庫の選び方や管理方法について、詳しく知りたい方は多いでしょう。
冷蔵倉庫の選定が不適切だと、商品の品質劣化や、想定外のコスト増加の原因となり、事業に影響を及ぼす可能性があります。
自社の商品に適した倉庫を選ぶことで、品質を保ちながら事業を拡大するためにも、適切な環境を備えた倉庫を選定することが大切です。
今回は、冷蔵倉庫の基本的な知識から選び方のポイントまで解説します。冷蔵倉庫の利用を検討する際に、本記事の内容をお役立てください。
目次
冷蔵倉庫とは?
冷蔵倉庫とは、10℃以下の温度で保管される倉庫のことです。食品や医薬品をはじめとした温度管理が求められる商品の品質維持に利用されます。乳製品や精肉、鮮魚、野菜、果物などは、決められた温度で管理しないと品質が落ちてしまいます。そのため、上記のような商品の物流では冷蔵倉庫が活用されます。
また、冷蔵倉庫は生産から消費まで商品を低温でつなぐ物流の仕組み「コールドチェーン」を支える施設でもあります。適切な温度で保管すると食品衛生上のリスクが減り、品質を保った商品を安定して供給しやすくなります。
なお、倉庫業法では、冷蔵倉庫をC級(チルド級)とF(フローズン)級で分類されています。そして、冷蔵倉庫より低い温度で保管できる設備を整えている倉庫を冷凍倉庫と言います。これらの温度区分は、商品の鮮度保持や食品安全管理のために守るべき基準です。
参考:倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示」の改正について
冷蔵倉庫の仕組みや設備
冷蔵倉庫は、内部の温度や在庫を適切に管理するため、専用の設備やシステムを備えています。商品ごとに適した温度が異なり、厳密な衛生管理も求められます。
冷蔵倉庫内は「チルド区画」や「低温区画」のように複数の温度帯に分けて管理することも多いです。
温度はセンサーで常に監視し、異常があれば警告を発する仕組みが一般的です。衛生面では、食品の安全を守る国際的な管理手法であるHACCPに沿った管理を行なう倉庫もあります。
また、多くの倉庫がITシステムを活用しています。在庫の状況を正確に把握するWMS(倉庫管理システム)や、受注情報を管理するOMS(受注管理システム)などがその一例です。
これらの仕組みが、商品の品質を守り、効率的な物流を支えています。
冷蔵倉庫の導入メリット
冷蔵倉庫には主に以下の3つのメリットがあります。
- 商品ロスの削減
- 商品の品質保持
- 営業エリアの拡大
ひとつずつ見ていきましょう。
商品ロスの削減
冷蔵倉庫の利用は、商品の廃棄リスクを減らすことにつながります。食品や医薬品は温度の変化に弱く、適切な管理をしないと品質がすぐに落ちてしまうためです。
冷蔵倉庫で在庫を管理すると、廃棄率をおさえて原価のロスを少なくできます。特に、生産から消費まで低温を保つ物流網「コールドチェーン」の一環として活用すれば、品質トラブルを防ぎ、安定した商品供給に貢献できるでしょう。
商品の品質保持
冷蔵倉庫は、商品の鮮度や風味、栄養価などを高い水準で維持するのに役立ちます。庫内を商品に適した温度帯に保つことで、食品の酸化や腐敗といった劣化の進行を遅らせるためです。
医薬品や化粧品なども温度変化に弱い品物として挙げられます。そのため、一定の温度での管理は品質を保証するうえで大切です。商品の品質を安定させると、顧客満足度やブランド価値の向上も期待できます。
営業エリアの拡大
冷蔵倉庫の活用は、販売エリアを広げることにつなげられます。鮮度を保ったまま遠方の顧客へ商品を出荷しやすくなり、これまで地域限定だった販路を全国へ広げられるでしょう。
さらに、複数の拠点を組み合わせれば、配送時間を短くし、顧客に届けるまでのリードタイムを改善する効果も見込めます。結果として、売上の増加や新たな市場の開拓につながります。
冷蔵倉庫のデメリット
冷蔵倉庫にはメリットがある一方、いくつか注意点もあります。導入を検討する際は、コストやリスクといった側面も理解しておく必要があります。
高コスト
冷蔵倉庫は、設備投資や維持管理の費用が高くなる傾向にあります。
庫内の温度を低温で安定させるには高性能な冷却設備が欠かせず、電気代も一般的な倉庫に比べて高額になるためです。
自社で倉庫を建てる場合は多額の初期投資を要することから、外部の委託倉庫を利用する企業も少なくありません。
温度トラブル時のリスク
停電や設備の故障で、庫内の温度を一定に保てなくなるリスクも考えられます。
特に冷蔵・冷凍品は温度の変化に弱く、一度でも基準の温度を超えてしまうと、品質が損なわれ再出荷できなくなる恐れがあります。
万一の事態に備え、バックアップ電源や温度監視システムが整った倉庫を選ぶことが大切です。
立地の制約
冷蔵倉庫は特殊な設備を要するため、建てられる場所が限られることがあります。
配送効率を上げるために、顧客が多いエリアや主要な高速道路の近くに集中して設置されることが多く、地方によっては選択肢が少ないという実情があるのです。
需要のあるエリアになるべく近い倉庫を選ぶことが、物流コストを抑えることにつながります。
冷蔵倉庫業者を選定する際のポイント
冷蔵倉庫を選ぶ際には、いくつか確認すべき点があります。自社の商品に適した業者を見つけるために、これから解説する4つのポイントを参考にしてください。
自社商品の温度帯に対応しているか
まず、候補となる倉庫が自社商品の保管に必要な温度帯を維持できるか確認しましょう。
冷蔵倉庫はC級やF級などの複数の温度区分にわかれており、商品ごとに適した保管温度が定められています。
たとえば、精肉や鮮魚などの生鮮食品は、わずかな温度変化でも品質が大きく落ちてしまいます。医薬品や化粧品のように厳密な管理が求められる商品では、センサーによる常時監視や警報システムの有無も確かめたい点です。
庫内を複数の区画に分けて管理するゾーニングに対応しているかも、あわせて確認しましょう。
自社商品と似たジャンルの商品の保管実績があるか
自社の商品と似たジャンルの取り扱い実績が豊富にあるかも事前に確認が必要です。
食品や医薬品といった分野によって、求められる温度管理の精度や衛生基準は異なります。
関連商品の取り扱い経験が豊富な業者ほど、適切な管理体制や運営ノウハウを持っていると判断できます。
たとえば、鮮魚を多く扱う業者なら迅速な入出庫体制が、医薬品を専門とするなら法令に準拠した管理体制が整っているはずです。
ISO認証(品質管理などが国際基準を満たしている証明)や、HACCP(食品の安全を確保するための衛生管理手法)などの客観的な指標も、業者の信頼性を判断する材料になります。
WMS/OMSと連携できるか
EC事業や多店舗展開を行なう場合、倉庫の管理システムと自社のシステムが連携できるかは確認すべきポイントです。在庫や受注情報を正確に共有できないと、欠品や誤出荷といった問題につながるためです。
倉庫管理システム(WMS)や受注管理システム(OMS)とリアルタイムで連携できれば、これらのリスクを減らせます。
特に複数の通販サイトで販売しているなら、情報を一元管理できる仕組みは業務効率に大きく影響します。API連携に対応しているかなど、自社のIT環境に合うかも確認しましょう。
サポート体制や温度トラブル時の対応力はあるか
停電や設備故障といった万一の事態に備え、業者のサポート体制や緊急時の対応力を事前に把握しておきましょう。冷蔵倉庫での温度トラブルは、商品の品質劣化につながるためです。
具体的には、24時間365日の監視体制、バックアップ電源の有無、トラブル発生時の対応手順が明確になっているかなどを事前に確かめます。定期的な設備点検を積極的に行なっているかどうかも、信頼できる業者を見分ける判断基準のひとつです。
まとめ
冷蔵倉庫は10℃以下の温度管理で商品の品質を保つ施設であり、商品ロスの削減や販路の拡大に役立ちます。しかしその一方で、導入コストの高さや温度トラブルといったリスクも考慮しなくてはなりません。ぜひ、本記事の内容を参考にして自社の事業に合った冷蔵倉庫を選び、安定した物流体制を構築しましょう。