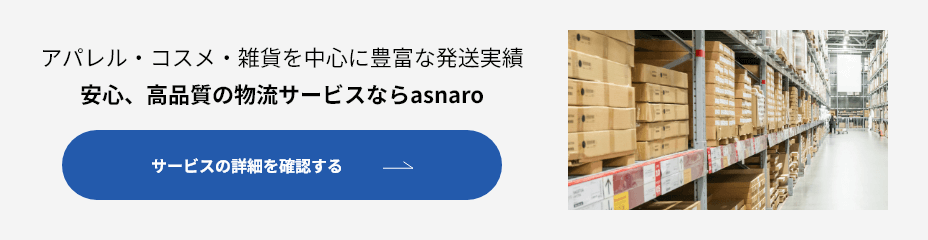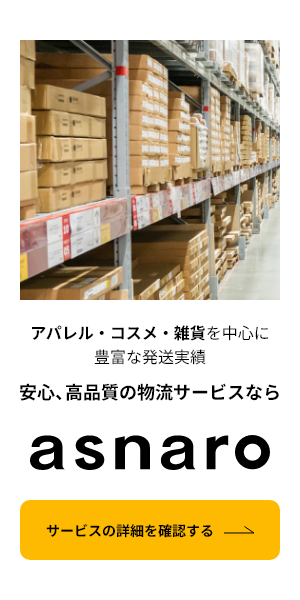先入れ先出しとは?導入メリットや実践するための運用方法を解説

物流倉庫の在庫管理の現場で欠かせないのが「先入れ先出し(FIFO:First In First Out)」という考え方です。
これは、最初に入庫した商品から順に出庫する仕組みで、在庫の鮮度を保ち、廃棄や品質劣化を防ぐ基本ルールです。
この記事では、先入れ先出しの仕組みやメリット、実践方法を解説します。効率的な在庫管理体制を構築したい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
在庫管理における先入れ先出しとは?
先入れ先出しとは、倉庫に入荷した商品を順番通りに出庫していく在庫管理の方法です。先に入庫した商品から優先的に出荷されるため、在庫が滞留しにくく、品質劣化や賞味期限切れを防ぐ効果があります。入荷順と出荷順を一致させることで、在庫の循環を自然に作り出し、効率的な商品回転を実現できるのが特徴です。
他の方式として「後入先出し(LIFO)」や「ランダム出庫」がありますが、LIFOはコスト計算に用いられるケースが多いため、実務上は鮮度や品質保持を重視するFIFOが主流となっています。FIFOは、食品や医薬品、化粧品など、劣化や期限がある商品だけでなく、あらゆる業種で効率化を実現する基本的な考え方としても知られています。
先入れ先出しを導入するメリット
先入れ先出しには、次のようなメリットがあります。
廃棄ロスや在庫ロスを削減できる
先入れ先出しを導入すれば、古い在庫から出荷されるため、倉庫内に滞留する商品が減少します。
結果として、期限切れや型落ちによる廃棄リスクを大幅に抑えることができます。
在庫ロス削減はそのままコスト削減につながり、利益率の改善にも寄与します。
商品の品質劣化や賞味期限切れのリスクを低減できる
先入れ先出しを徹底すると、長期間倉庫に放置される商品がなくなり、常に新鮮な商品を出荷できます。特に食品や医薬品では品質保持が最優先事項です。
先入れ先出しは、賞味期限切れを防ぐ仕組みとして極めて有効と言えます。
在庫回転率を改善できる
先入れ先出しにより在庫がスムーズに回転すれば、過剰在庫を抱えるリスクが減り、売れ残りを防げます。これにより、在庫回転率が向上し、資金の固定化を防止できます。
結果的にキャッシュフローも改善し、経営基盤の安定につながります。
倉庫内の作業効率が向上する
先入れ先出しを導入すると、在庫の配置や出庫順が明確になり、倉庫スタッフが迷わず作業できます。
無駄な動線や確認作業が減り、ピッキングや出庫作業の効率も向上。結果的に作業スピードが上がり、人的コスト削減につながります。
先入れ先出しを実践するための運用方法
商品保管の配置ルールを整備する
先入れ先出しを実現するには、まず商品の保管ルールを整備することが欠かせません。
入庫した商品を奥に、先に入った商品を手前に配置するなど、物理的に「先入れ」を前面に出せる仕組みを作る必要があります。
このルールを徹底すれば、スタッフは自然と古い在庫から出庫でき、管理が簡単になります。
倉庫内のレイアウトを工夫する
倉庫の通路設計や棚配置を工夫することで、先入れ先出しはよりスムーズに機能します。
フローラックやパレットフローを導入すれば、前から取り出し後方から補充する動線が自然に作られ、先入れ先出しが自動的に実現します。
物理的なレイアウト改善は、検品やピッキング精度の向上にも直結します。
ロット番号や賞味期限のラベル仕様や登録方法を工夫する
先入れ先出しを確実にするには、ロット番号や賞味期限を明確にラベル表示し、システムにも正しく登録することが重要です。
目視で判別しやすい位置に表示すれば、現場作業がスムーズになります。また、ラベルの統一ルールを定めることで誤出荷のリスクも防止できます。
ピッキングルール(古い在庫から順に出庫)を標準化する
ピッキング時には必ず古い在庫から出庫するルールを標準化し、スタッフに徹底させる必要があります。
曖昧な運用ではルールの逸脱が発生し、先入れ先出しが機能しなくなります。マニュアルや教育を通じて、現場全員に理解と実践を浸透させることが大切です。
倉庫管理システム(WMS)などでロット管理する
システムを活用すれば、入庫順やロット情報をデータで管理でき、ピッキングリストに古い在庫を優先的に表示することが可能です。
手作業に比べてヒューマンエラーが大幅に減少し、効率と精度の両立が図れます。特に大規模倉庫や多品種商品を扱う現場では、WMSやERPの活用がポイントです。
運用ルールをマニュアル化する
先入れ先出しを長期的に機能させるためには、明確なルールをマニュアル化し、全スタッフに浸透させることが重要です。
誰が作業しても同じ品質で検品・出庫できるよう標準化すれば、属人化を防ぎ、安定した運用が可能になります。
定期的にマニュアルを見直し、改善を続けることも欠かせません。
先入れ先出しを導入する際の注意点
管理工数が増えスタッフの負荷が大きくなりやすい
先入れ先出しを導入すると、入庫順やロット管理を徹底する必要があるため、作業工程が複雑になりがちです。
スタッフは数量や期限の確認に加えて、在庫の順序管理も求められるため、現場の負担が増加します。
教育やシステム活用で効率化を図らなければ、人件費の増大や作業遅延につながる可能性があります。
棚替えや移動作業、配置替えの手間が起きる
先入れ先出しを徹底するためには、在庫を古い順に前方へ移動したり、棚替えを行なったりする手間が発生します。
特に大量在庫を扱う現場では、配置替えに多くの時間と労力が必要となります。
こうした負担を軽減するには、フローラックなど物理的に先入れ先出しを実現できる設備を導入するのがおすすめです。
長期保存品などでは過剰な運用コストがかかる
先入れ先出しは賞味期限や劣化リスクが高い商品に有効ですが、長期保存が可能な商品では必ずしも必要ではありません。すべての商品に適用すると、逆に管理工数やコストが増える恐れがあります。
対象商品の選定を誤ると、かえって効率が下がるため、導入前に十分な検討が必要です。
運用ミスが起きると出庫順が崩れるリスクがある
先入れ先出しはルールを守ってこそ機能するものです。
担当者が誤って新しい在庫を先に出庫してしまうと、出庫順が崩れ、古い在庫が滞留する原因になります。
特に人手作業中心の現場ではミスの可能性が高く、チェック体制やシステム支援を導入してルール逸脱を防ぐことが欠かせません。
先入れ先出しを導入するステップ
現状(保管状況やリソースなど)を分析する
先入れ先出し導入の第一歩は、現状の在庫管理体制を正しく把握することです。
倉庫内の保管状況や動線、在庫回転率、人員配置、使用しているシステムなどを分析し、どこにロスや非効率が生じているのかを明確にします。
たとえば、同じ商品が複数の棚に分散して置かれている場合、出庫順序が乱れやすく、先入れ先出しは難しくなります。
現状分析によって課題を洗い出し、改善の優先順位をつけることで、無理のない導入計画が立てられます。
また、現場スタッフへのヒアリングを通じて実際の作業フローを把握し、理想と現実のギャップを確認することも重要です。
先入れ先出し対象商品を選定する(リスク高商品、賞味期限品など)
すべての商品に先入れ先出しを適用すると、かえって工数やコストが増えます。そのため、導入初期は対象商品を選定することが重要です。
通常、食品や医薬品、化粧品といった賞味期限や消費期限がある商品、また劣化しやすい商品は最優先で先入れ先出しを導入すべき対象です。
一方で、長期保存が可能な商品や劣化リスクが低いものは、必ずしも先入れ先出しの対象にする必要はありません。
運用ルールを設計し、マニュアル化する
先入れ先出しを効果的に機能させるには、現場で守るべきルールを明確に設計し、マニュアル化することが欠かせません。
具体的には
「入庫した商品を必ず指定の場所に配置する」
「ピッキング時は古い在庫から出す」
「ロット番号と賞味期限を必ず確認する」
などのルールを定めることがポイントです。そして、これらを文書化して全スタッフに共有し、誰が作業しても同じ品質で検品・出庫ができるようにします。
マニュアル化は属人化を防ぎ、繁忙期や新人スタッフが多い時期でも安定した運用を実現します。
また、単なる手順書として終わらせず、教育・研修のツールとして活用することもできます。
試行導入し、現場パイロット運用する
いきなり全体導入すると混乱が生じる可能性が高いです。まずは特定の商品やエリアで試行導入するのが効果的です。
小規模なパイロット運用を行なうことで、現場の動線やオペレーションにどのような影響が出るかを検証できます。たとえば、棚の配置やラベル表示のわかりやすさ、システム入力の手間など、実際に運用してみなければわからない課題が浮き彫りになります。
試行段階で得られた改善点を反映し、ルールを微調整してから全体導入に移行することで、スムーズに先入れ先出し体制を構築できます。
モニタリングし、KPI(在庫滞留率、廃棄率、出荷ミス率など)を設定する
先入れ先出し導入の効果を正しく把握するためには、定量的なKPIを設定してモニタリングすることが不可欠です。在庫滞留率や廃棄率、出荷ミス率などを指標として定期的に確認すれば、導入効果が数値で可視化されます。
たとえば、導入前後で廃棄率がどの程度改善されたかを比較することで、施策の有効性を判断できます。KPIを設定することで、現場スタッフも成果を意識しやすくなり、モチベーション向上にもつながります。
改善サイクル(PDCA)を回す
FIFOは一度導入すれば終わりではなく、継続的な改善が必要なものです。計画(Plan)を立て、現場で実行(Do)し、成果を評価(Check)したうえで、改善策(Act)を反映させるPDCAサイクルを回しましょう。
たとえば、廃棄率が思うように下がらない場合は、対象商品の見直しや棚配置の改善を検討します。このプロセスを繰り返すことで、現場に合った最適な先入れ先出し運用を構築できます。
まとめ
先入れ先出しは、在庫ロスを防ぎ商品の品質を保つ基本的な在庫管理の手法です。
導入には工数やコスト面での負担がありますが、対象商品の選定やルール設計を工夫すれば効果的に運用できます。
小さく始めて改善を重ね、効率的な在庫管理体制を築きましょう。
よくある質問
先入れ先出し(FIFO)とは?「物流 先入れ先出し」の基本を教えてください。
入庫が早い在庫から優先して出庫する在庫管理の原則です。物流現場では滞留在庫や劣化・賞味期限切れを防ぎ、在庫回転率を上げる目的で運用します。 英語では FIFO(First In, First Out)と表記します。
先入れ先出しを徹底するメリット・デメリットは?
メリットは廃棄・値引きロスの削減、在庫鮮度の維持、キャッシュフロー改善です。 デメリットはレイアウト制約やオペレーション工数の増加(動線・補充)が発生しやすい点。WMSやロケーション最適化で工数増を抑えられます。
WMSやバーコード/RFIDでのFIFO管理ポイントは?
ロット・入庫日・シリアルの必須化、ピッキング指示の「古い順」ロジック、先入れ先出し違反時のアラートが鍵です。ハンディで入庫日スキャン→WMSが出庫順を指示、という運用にすると現場ブレが減ります。
先入れ先出しを実現するレイアウトや棚の組み方は?
最も効果的なのは「フローラック」の導入です。傾斜のあるロ-ラー棚で補充口と取り出し口を分離し、重力により古い商品が自動的に手前に流れる構造です。 通常の棚では新しい商品を奥、古い商品を手前に配置し、U字型レイアウトで入庫・出庫動線を明確に分けることが重要です。
先入れ先出しとLIFO(後入れ先出し)の違いと使い分けは?
LIFOは最後に入庫した商品から出庫する手法で、主に会計上のコスト計算に使用されます。 実際の物流現場では商品の鮮度や品質保持を重視するためFIFOが主流で、LIFOは古い在庫の滞留リスクがあるため避けられています。